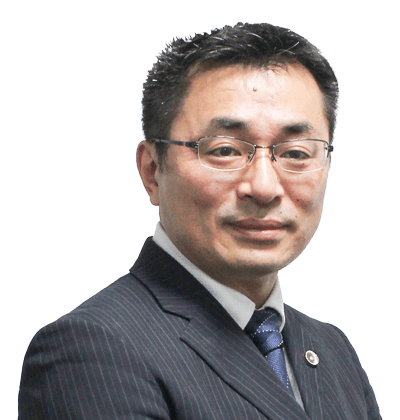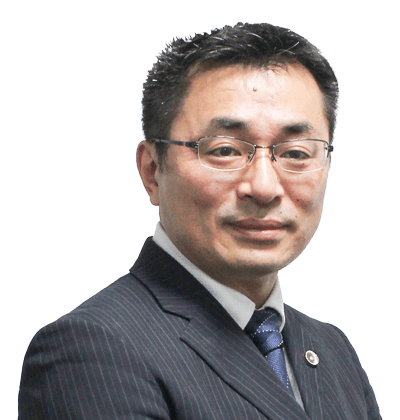本日は、不当利得返還請求権のことについて書きたいと思います。
この請求権は我々弁護士にとっては、使い勝手の良い請求権である反面、その請求権が成立す
・・・(続きはこちら) 本日は、不当利得返還請求権のことについて書きたいと思います。
この請求権は我々弁護士にとっては、使い勝手の良い請求権である反面、その請求権が成立するかどうか、悩むこともあります。
1 使い勝手の良い請求権
⑴ 民法上、色々な契約に基づく請求権が定められています。
売買契約に基づく売買代金請求権、
賃貸借契約に基づく賃料請求権、
請負契約に基づく請負代金請求権・・・。
そんな請求権の中で、不当利得返還請求権は、そういった民法上の定めのない領域でも、民事上の請求権として認められる可能性を持った「補充的な」請求権とも言われています。
民法に定めのある請求権のカタログに当てはまらければ、不当利得の成否を考えよう、というわけです。
今までに、不当利得返還請求権の対象と認められたものとしては、
ア 過払い金返還請求権
イ 遺産の使い込みがあった場合の返還請求権、
ウ 契約が無効になった場合の返還請求権、
エ 誤振込があった場合の金銭返還請求権
などがあります。
⑵ 特に有名なのが、アの過払い金返還請求権。
金融会社が違法な金利を取っていた場合、違法な金利を取った範囲で借主に返還するべし、という内容なのですが、法律上は不当利得返還請求権で観念される、と言われています。
以前出てきた不法行為に基づく損害賠償請求、又は債務不履行に基づく損害賠償請求という構成も、なくはないのですが、
ア 過払い金が発生したことについて、受益者の故意過失をどう主張立証するかという問題(不法行為・債務不履行共通)、
イ 過去に違法な金利で弁済を受けた、ということが、金融会社にとって何の債務不履 行にあたるのか、という債務不履行内容特定の問題
が生じ、請求をするのが容易ではなくなります。
その点、不当利得返還請求権は
ア 請求側の立証責任負担は大きくない(違法かどうか、故意過失があるかの問題などは、「基本的には」出てこない。)
イ 債務の内容を特定しなくとも、法律上の原因なくある者が利得を受け、反面他の者が損失を受け、その利得と損失との間に因果関係があれば要件を満たすと言われています。
なお、かかる過払い金返還請求における、長年にわたる金融機関との訴訟などにより、この不当利得に関する議論が更に深まったこともあるのですが、それは別稿に譲ります。
2 不当利得が成立するのかどうか
⑴ 一方、事案によっては不当利得が成立するかどうか、明確ではない、というケースもあり、頭を悩ませることもあります。
ア 遺産の使い込みがあった場合の返還請求権において、対象である預金口座から、誰がお金を下したのかわからない場合(利得を得たのは誰か?)
イ 誤振込があった場合の金銭返還請求において、諸事情により、振り込まれた口座の特定ができない場合(利得を得たのは誰か?)。
ウ 契約が無効になった場合の不当利得返還請求として、どこまでが「利得」として認められるのか(利得の範囲。解除した者の言い分が全部認められるのか?)。
⑵ また、不当利得の成否を検討するにあたり、明文に定めはないのですが、公平の観点から不当利得を認めるのが妥当かどうか、を実質的な要件とすべき、という考え方もあります。
このような考え方は、「公平」という曖昧な基準により、不当利得の成否が委ねられることから、法的安定性を欠く(不当利得が認められるかどうか、『より』わかんなくなる)と批判されることもあります。
しかし不当利得返還請求権を認める趣旨が、補充的な観点から、当事者の公平維持を図ることではあるので、そのような要件を付け加えることもやむを得ないのではないか、と思います。
3 このように不当利得返還請求権は、事案に登場する場面も多いのですが、その請求権の成否が問題になることも多いです。
弁護士として、事案解決のために、カタログとしての民法に定められた請求権の内容を知悉し、活用することは当然として、不当利得返還請求権の成否についても頭を巡らすことが重要なのではないか、と思います。
以上